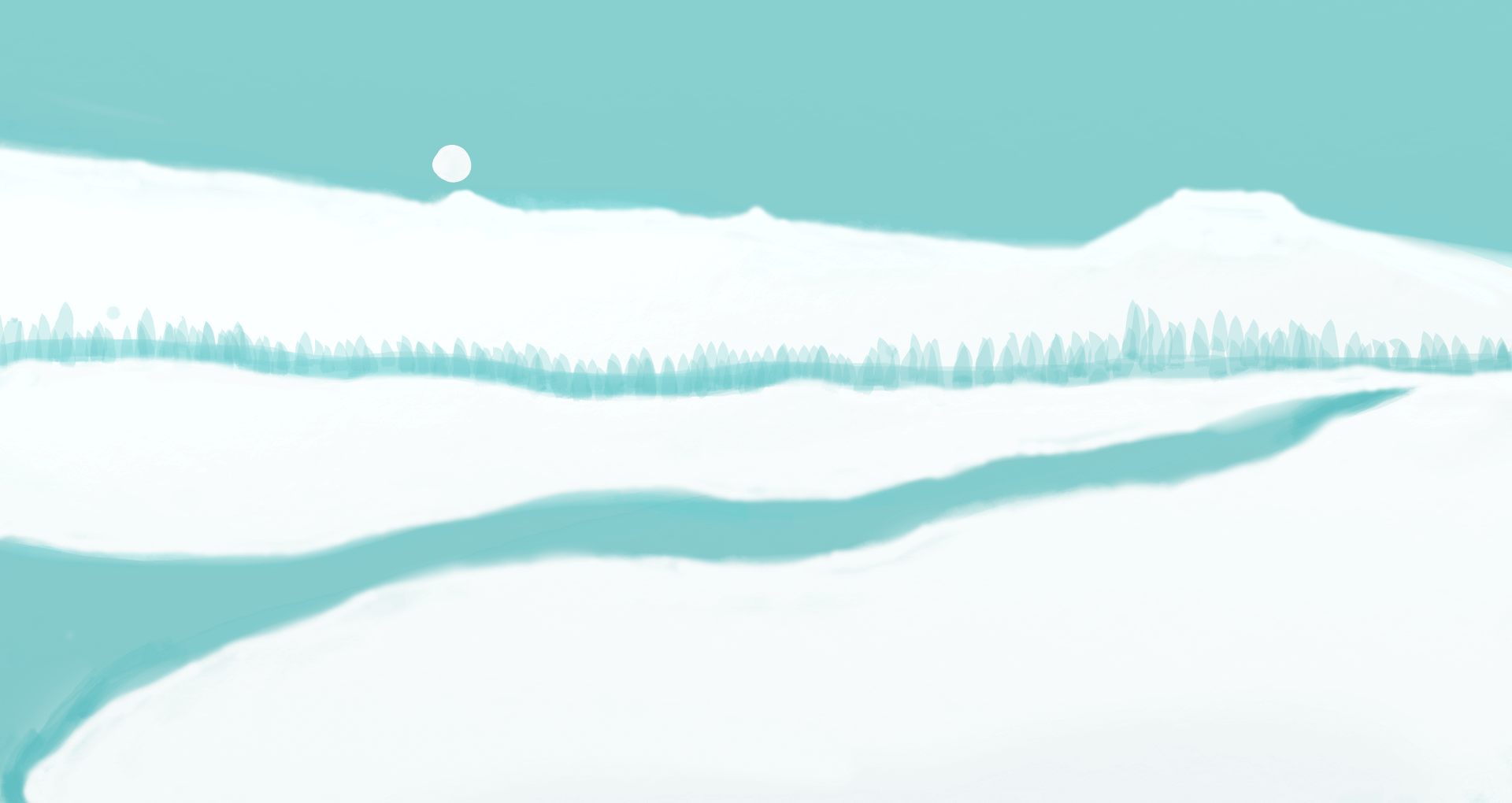テント泊の夜に見た夢。
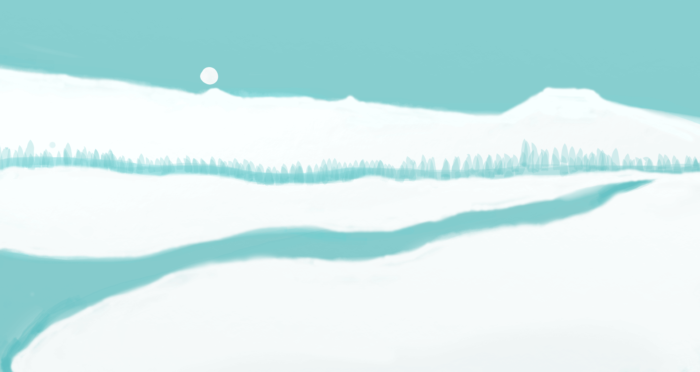
「おい、できたぞ」という声とともに暗い天幕の中にいっせいに光が射し込み入口から男が顔を覗かせた。男は僕の返事を確認すると直ぐにどこかへ行ってしまった。逆光により男の表情は確認出来なかったけれど、僕は彼を知っているようだった。いや、声をかけられテントを不躾に開けられても驚きも苛立ちも覚えないのだから家族や友人といった親しい間柄であるのかもしれない。しかしながら僕は彼が誰であるのか分からなかった。にもかかわらず、誰だか知らない馴染みの彼に「わかった」とか「はいよ」といった返事を僕はしたようだ。
「あぁ、これは夢だな。」
僕は睡眠中に夢を見ながら「これは夢だな」と気がつくことがある。そういう時は決まってそのまま夢の続きを見るのだけど、それがどんなに無残で残酷な夢であろうが嬉し泣きに咽びこむほどの幸せな夢だろうがおかまいなしで覚めるまで見続け、そして唐突に打ち切られる。この夜の夢もまた夢であることに気がつきつつ、夢と意識の間を過ごすことになった。
「やれやれ」僕は胸の内で呟く。
僕は小さいため息をついてから重そうに体を起こし光の射し込む天幕の入口へと動きだす。そして、足下が確認できない不安な暗闇をのそのそと入口まで辿り着くと左手で勢いよく入口の帆を開いた。その瞬間、僕は顔をしかめ瞼をきつく閉じた。開いた瞳孔に飛び込んできた光が刺すように痛い。
「くそっ」
そんな言葉を発しつつ、歯を食いしばり、下を向き、右腕で目を覆いながら痛みに耐えようとする僕をよそに痛みが治まるのを待たず体は薄目をあけ足下を見る。雪が積もった足下が映り、顔をあげ辺りを見渡すと雪原の中にいることが分かった。雪原は山に囲まれており、稜線のわずか上空には太陽が確認できた。鼻から空気を吸い込むと冷気で鼻腔がつんと痛む。冬の空気だ。僕が昨夜に寝付いた季節は初夏だといのに、この世界は冬。吐く息は深く重い白色で空に舞い上がることははなかった。
物事はすいすいと流れていく。そして、その流れに逆らうことなく僕もすいすいと過ごしていく。ただ、意識だけは常に遅れをとっていて転校初日の小学生のような気分だ。
「おい!どうした!はやくこいよ!」
声のする方に顔を向けると馴染の彼が呼ぶ声がする。雪原の中には小川が流れていて、彼はそこから少し離れた場所で煮炊きをしていた。どうやら食事の支度をしていたようだ。彼のもとへ歩いていくと火元の脇に倒木があり、そこが僕の定位置なのだろう、僕は黙ってそこに腰を降ろした。
「よく寝てたな。少しは元気でたか?」
こちらに背を向けたままそう言った馴染みの彼に「まぁね」とか「うん」といった簡単な返事を僕はしたようだ。そして、すぐに小川に視線は移った。小川は1メートルほど積もった雪で覆われて、本来の川幅よりもずっと狭くなっているのだろう。岸際に不用意に近づくと雪を踏み抜き川に落ちそうだった。
そろそろ状況の整理が必要だ。まず、僕たちは雪原の中にいる。馴染の彼は飯の支度をしていて、これから食事をするようだ。彼の服装は動物の皮でできた上着を着ていて、詳細はわからないけど、ずいぶん昔の山賊のような恰好をしている。そして、怪我か風邪か失恋のとめな…どうやら僕はとにかく元気がないらしい。
「ほら、できたぞ。食え」
唐突に彼が椀を差し出し、にんまり顔でそう言った。彼は顔に髭を蓄えているが僕と同じ年の頃だろうか。僕はだまって左手を差し出す。
「そっちの手じゃ椀が取れねぇだろ。それに手ぬぐいはどうした?」
何を言っているのか分からず。僕は差し出した左手に視線を移すと、そこには指のない手の平があった。
僕は理由を理解した。
その手の詳細を説明するなら親指以外の指は第2関節より先がない。指の先端はつるりと丸まっていて、その内側にある関節の骨の形が少しばかり浮き出している。見るからに椀を上手に受けとることが困難であると分かる左手だった。
不思議なことに僕はその手をみてもまったく驚くことはなかった。ただ、そうはいっても突然に消えた指先に興味が沸かないはずがなく。僕は指の無い左手を観察し動作を確認した。
グーを握り、パーとひらく。続いてチョキを作ると、やれやれと少し落胆した。
「おいおい、大丈夫か?ちょっと左手だせや。」
いつまでも手わすらを止めない僕を見ていた彼がしびれを切らして言った。そして、自分ふところから、えんじ色の手拭いをだし僕の左の手のひらにぽんと置き、それから、手ぬぐいの上に椀を乗せ「こうだろ。食えよ」といった。
どうやら僕は左の手の平に手拭いを敷き、それから右手で椀をその上に置いて椀をすするようだ。
椀の中には白い汁が入っていたが具の詳細はもとより味すら分からなかった。というのも残念ながら僕は食べることなく物語は突然に食後の場面に変わってしまったからだ。
食後の場面に移ると、馴染の彼は鉄瓶から注いだ何かを椀で飲みながら左足をさすっていた。僕はといえば倒木に座りながら気になる左手の観察をしている。ふいに馴染の彼が椀を雪の地べたに置き空を見上げてから、さてと、僕のほう見て話はじめた。
「お前は手の指、俺は足の指、弥彦の爺さん(仮名)はあれから弱っちまったしな。」
「先週の嵐も酷かったが、あの冬は本当に酷かった…。」
「そういえば、爺さんとこ顔出せって婆さんが言ってたかなら手土産持っていかねぇとな。」
「今日は獲れるといんだが…。お前、すこし長く歩くけど大丈夫か?」
「準備してくっから、ここで温まってろ」
話を終えた馴染の彼は天幕の方へ歩いて行き。
彼が見えなくなったところで目が覚めた。
さて、彼の話といより独り言のような会話のような、そんな話を聞いているあいだ僕が入り込んだ夢の中の僕の記憶が見えていて馴染の彼の話をまとめるとこうだ。
馴染の彼は僕の叔父さんで、僕たちは天幕というより小屋のような物を雪原に建て、そこを起点に狩猟をしている猟師。数年前の冬のある日、猟にでた弥彦の爺さんと馴染の彼、そして僕と僕の父親は急な嵐のせいで山から出られなくなった。僕の父親はその時に亡くなっていて、叔父さんは左足の指、僕は左手の指を失くしている。弥彦の爺さんは僕の父親を探しにいって山中で遭難するも翌朝に天候が回復し自力で下山し山小屋に帰った。以来、爺さんは体が弱ってしまって猟にはでることができず、冬の猟には叔父さんである馴染みの彼と僕の二人でている。夢の中の僕はなぜか体調不調がちでその日も天幕のなかで休んでいた。この日は猟をいったん切り上げて村だか山小屋に帰る日で弥彦の爺さんが好きな獲物が獲れてはいないから、ちょっと獲物を探しながら遠回りして帰ろうということになっている。そして、叔父さんは出かける準備をするから僕はここで休んでいろということらしい。
ちなみに、夢の中の僕は中学生くらいで極度に口数が少ないようで彼の声を耳で捉えることはなかったし、彼の記憶を共有していてもそこに感情の起伏というものを全く感じることはできなかった。
僕は彼のなかから彼の世界を眺めるだけの存在として器に入った者。
そんな夢だった。